一番出汁と二番出汁の違いと使い分け|瀧さわ家の出汁基礎講座
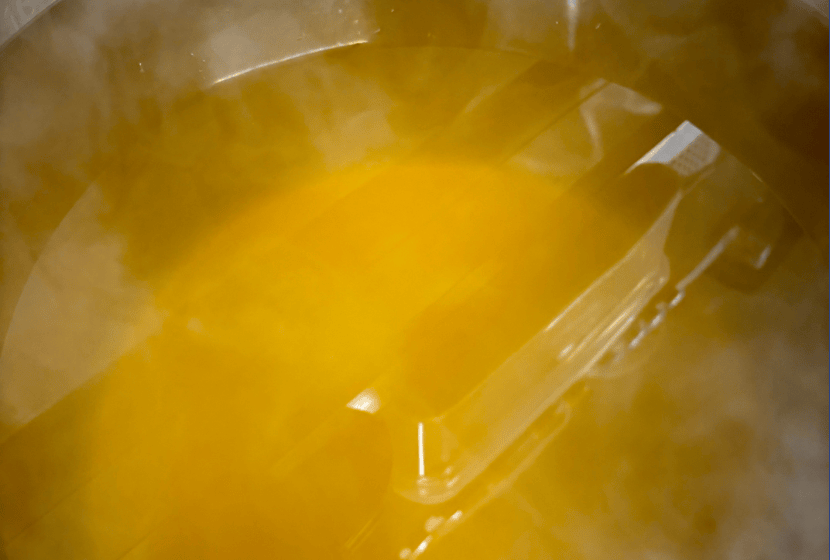
和食の要といえば「出汁」。 その出汁にも“一番”と“二番”の違いがあることをご存知でしょうか?
今回は、瀧さわ家の料理の根幹をなす「一番出汁」と、限定的に使う「二番出汁」について、それぞれの特性と考え方をお話しします。
一番出汁とは|澄みきった香りと旨みの核
一番出汁とは、昆布と鰹節(荒節)などから最初に取る出汁のこと。
- 火入れの温度と時間に細心の注意を払い、濁らず澄んだ状態で仕上げます。
- 香りが立ち、旨味がやわらかく広がる
- 苦味や渋みが出ない、最も繊細な出汁
瀧さわ家では、この一番出汁を主に:
- 茶碗蒸しの玉地
- 出汁巻き卵
- お吸い物の吸い地
- 繊細なあんかけのベース
など、“出汁そのもの”の質が問われる料理に使います。
二番出汁とは|深みとコクを引き出す“働き者”
一番出汁を取った後の昆布や鰹節に、さらに水と追い鰹を加えて取るのが「二番出汁」。
- 一番出汁よりも色が濃く、香りよりも“旨味の厚み”が前に出ます
- 少しの雑味や渋みも含まれるが、それが「深さ」にもなる
- 経済的かつ実用的
瀧さわ家では、二番出汁を主には使用せず、基本的には一番出汁のみで味を構成しています。
唯一の例外として、ランチで提供している「せいろ」の「つゆ」には、残った「つゆ」を最後まで楽しんでいただくように、二番出汁の無料提供を行っており、皆さまがその二番出汁で「つゆ」を薄め、お吸い物として食していただいています。かなり美味しいと評判です。
また、出汁は毎朝取り切り・使い切り。素材の香りと旨味を“新しいまま届ける”ことを何より大切にしています。
一番出汁で描く、料理の設計図
出汁は「良いものを使えば良い」だけではありません。
料理の種類や目的に応じて、どのような香りを立たせたいのか/どんな余韻を残したいのか。そこに合わせた組み立てが求められます。
瀧さわ家の料理設計は、一番出汁を前提にすべて組み立てられています。
その香りと旨味のバランスが、どの料理においても素材を引き立て、味の“軸”となるからです。
出汁の設計とは、素材を活かすための静かな算段。その日の温度や素材の状態によって、出汁の表情もまた変わります。
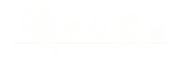
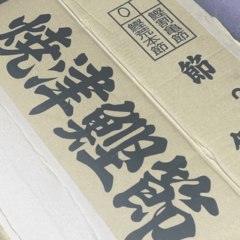

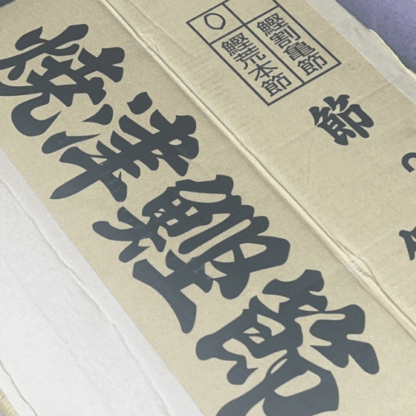

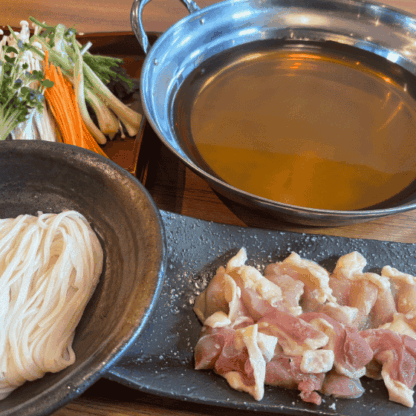




この記事へのコメントはありません。